 お散歩担当ゆうき
お散歩担当ゆうきお散歩から帰ってきたらブラッシングタイム!
ツヤツヤになろうね~~!



ワンちゃんが気持ちよさそうにしていると、私たちもうれしくなるね!
愛犬との暮らしの中で、ブラッシングはもっともお手軽で、導入しやすいお手入れ方法です。毛並みも良くなるし、犬とも仲良くなれるし、良いこと尽くめ。
しかし
・「どれくらいの頻度ですればいいの?」
・「正しいやり方がわからない」
・「どんなブラシを選べばいいの?」
・「うちの子、ブラッシングを嫌がるんだけど…」
といった疑問や悩みをお持ちの飼い主さんも多いのではないでしょうか?
この記事では、数々の犬をお世話してきたペットホテルまるまるハウスが、愛犬のブラッシングに関するあらゆる疑問にお答えします!
ブラッシングの驚くべき効果から、犬種や毛質に合わせた適切な頻度、初心者にも分かりやすい正しいやり方、愛犬にぴったりのブラシの選び方、そしてブラッシングが苦手な子への具体的なアプローチまで網羅的に解説します。
このガイドを読めば、あなたも愛犬のブラッシングマスターに!
愛犬の健康を守り、美しい毛並みを保ち、さらに絆を深めるためのヒントが満載です!
- ブラッシングの効果
- ブラシの種類と選び方のポイント
- ブラッシングの方法と嫌がる子へのコツ
毛並みを整えるだけじゃない!ブラッシングの効果


「ブラッシングって、毛並みを整えるためだけでしょ?」と思っていませんか?
実は、ブラッシングには見た目を良くする以外にも、愛犬の健康や飼い主さんとの関係性の向上や、皮膚炎の予防など、素晴らしい効果がたくさんあります。
抜け毛・毛玉の除去と皮膚炎の予防
ブラッシングは、抜け毛や絡まった毛を取り除き、毛玉ができるのを防ぎます。毛玉を放置すると、皮膚が引っ張られて痛みを感じたり、蒸れて皮膚炎の原因になったりすることもあります。
ブラッシングをすることで不要な毛を取り除き、被毛の通気性がよくなることで、ノミ、ダニの増殖やカビの増殖が防げます。皮膚炎になってしまうと症状が長引くことも多いので、こまめなブラッシングで解消したいです。
血行促進と皮膚の健康維持
ブラシで皮膚を適度に刺激することで血行が促進され、健康な皮膚と毛並みを育む助けになります。マッサージ効果もあり、愛犬をリラックスさせることもできます。
リラックス=ストレス軽減です。ストレスが軽減すると代謝がよくなったり、体質が改善したりするので、ブラッシングは結果的に全身の健康に影響するということです。
皮膚の異常や寄生虫の早期発見
体全体をブラッシングすることで、普段気づきにくい皮膚の赤み、湿疹、できもの、フケ、ノミやダニなどの寄生虫を早期に発見できます。病気の早期発見・早期治療に繋がります。
犬たちは人間の簡単な言葉を理解はできても、自らお話しすることはできません。飼い主として、犬たちの心の声を知れるように、ブラッシングを通して体の変化に気づいてあげたいですね。
美しい毛並みの維持
定期的なブラッシングは、毛のもつれを防ぎ、毛に付着したホコリや汚れを取り除くことで、健康的で美しいツヤのある毛並みを保ちます。
たまに見るサラサラフワフワの毛並みの良い犬は、実は良いシャンプーだけではなく、ブラッシングを毎日やってもらっているのかもしれませんね。
愛犬とのコミュニケーション深化
ブラッシングは、愛犬との大切なスキンシップの時間です。優しく声をかけながら行うことで、犬は安心感を覚え、飼い主さんとの信頼関係が深まります。体を触られることに慣れさせる良い機会にもなります。



幼いうちからブラッシングを取り入れることで、信頼関係×良い毛並み、どちらも得られますね!
ブラッシングの適切な頻度|毛の長さ・毛質別に解説
ブラッシングの頻度は、犬の状態、犬種や毛の長さ、毛質によって異なります。愛犬に合った頻度で行うことが大切です。
毛の長さによる違い
犬の毛の長さによる違いは大きく分けて2種類あります。
短毛種


頻度: 週に1~2回程度
ポイント: 抜け毛は少ないですが、皮膚のマッサージや血行促進、汚れ落としのために定期的に行いましょう。ラバーブラシなどがおすすめ。
長毛種


頻度: 毎日~2日に1回
ポイント: 毛が絡まりやすく毛玉ができやすいため、毎日のブラッシングが理想です。放置するとフェルト状の毛玉になり、皮膚トラブルの原因にもなります。
毛の生え方による違い
毛の生え方は、主にシングルコートとダブルコートの2つのタイプに分かれます。
シングルコート


頻度:毎日
ポイント:被毛が一層構造(オーバーコートのみ)になっています。 抜け毛は比較的少ない傾向にありますが、毛が絡まりやすい犬種もいます。
ダブルコート


頻度: 毎日が理想
ポイント: アンダーコート(下毛)とオーバーコート(上毛)の二層構造になっており、特に春と秋の換毛期には驚くほど大量の毛が抜けます。
その他毛質による違い
カーリーコート


頻度: 毎日
ポイント: 巻き毛は非常に絡まりやすく、毛玉ができやすいのが特徴です。毎日のブラッシングで毛玉を防ぎましょう。スリッカーブラシやピンブラシが適しています。



どの種類の犬も基本的には毎日ブラッシングしてもいいんだね!



毎日やってもいいけど、長時間やりすぎると皮膚を傷めてしまうことがあるから、気をつけてね!
ブラシの種類と選び方のポイント


様々な種類のブラシがあり、それぞれに特徴と適した用途があります。愛犬の毛質や目的に合わせて最適なものを選びましょう。ブラシの特徴を頭に入れながらブラッシングを行うことで、効果を高めることができます。
スリッカーブラシ←万能!
ヘッドに、「く」の字に曲がった細い金属製のピンがズラーっと植えられています 。ピンの硬さにはソフトタイプとハードタイプがあり、皮膚を傷つけないようにピンの先端に保護用の丸いガードが付いているものもあります。
ピンブラシ
人間用のヘアブラシに似ています。長くまっすぐなピンが、ゴムやクッション性のあるヘッドから出ています 。ピンの先端は丸くなっていることが多いです 。
ラバーブラシ
全体がゴムやシリコンでできており、短い突起やブラシ状になっていることが特徴なブラシです 。手にはめるグローブタイプもあります 。
※長毛種やダブルコートの犬のもつれ解消やアンダーコート除去には、効果が薄いです 。
コーム(櫛)
金属製またはプラスチック製の歯が一列に並んでいます 。多くは、歯の間隔が広い部分(粗目)と狭い部分(細目)が一体になっています 。
獣毛ブラシ
豚毛、猪毛、馬毛などの天然毛、またはそれらの混合毛が使われています 。毛の硬さは、一般的に猪毛が最も硬く、次いで豚毛、馬毛の順に柔らかくなります 。
※もつれや毛玉の除去、大量の抜け毛取りには向きません 。
被毛タイプ別ブラシ選択ガイド表
ブラッシングに慣れてきて、もっと効果的なブラッシングがしたいと思うようになってきたら、毛質に合わせて最適なブラシを用意して挑戦してみましょう!
| 被毛タイプ | 主なブラシ | 仕上げブラシ |
|---|---|---|
| 超短毛 | ラバーブラシ | 獣毛ブラシ(柔らかめ) |
| 短毛・ダブルコート | スリッカーブラシ、ラバーブラシ | コーム、獣毛ブラシ |
| 長毛・シングルコート | ピンブラシ、コーム | 獣毛ブラシ(柔らかめ)、(毛玉に)スリッカー |
| 長毛・ダブルコート | スリッカーブラシ、ピンブラシ、コーム | 獣毛ブラシ |
| カーリーコート | スリッカーブラシ、ピンブラシ、コーム | 獣毛ブラシ(硬めも考慮) |
超短毛
例:ミニチュア・ピンシャー、ビーグル、ラブラドール・レトリバー、パグ、チワワ(短い毛の子)
メイン: ラバーブラシ
仕上げ: 獣毛ブラシ
(ダブルコートの場合) 換毛期: スリッカーブラシ
短毛・ダブルコート
例:柴犬、コーギー、ハスキー
メイン: スリッカーブラシ 。ラバーブラシも効果的 。
仕上げ: コーム 、獣毛ブラシ
長毛・シングルコート
例:ヨークシャー・テリア、マルチーズ、シーズー (長く伸ばしている場合)
メイン: ピンブラシ、コーム
仕上げ: 獣毛ブラシ
長毛・ダブルコート
例:ゴールデン・レトリバー、ポメラニアン、ボーダー・コリー、ロングコート・チワワ
メイン: スリッカーブラシ、ピンブラシ、コーム
仕上げ: 獣毛ブラシ
カーリーコート
例:プードル、ビション・フリーゼ
メイン: スリッカーブラシ
仕上げ: 獣毛ブラシ
おすすめブラシ紹介
まるまるハウスでは散歩後にブラッシングタイムを設けています。ブラッシングが大丈夫な子、苦手な子、様々なので、犬の性格や特性に合わせて使うブラシを使い分けるようにしています。
実際にまるまるハウスで使っているブラシを2つ紹介します!よかったら参考にしてみてください!
SanMori スリッカーブラシ



まずは、万能選手のスリッカーブラシから!
SanMoriのスリッカーブラシです!このブラシの良いところは、何といってもボタン一つで取った毛を外せる機能がついているところ。
この機能がないと間に挟まった毛をきれいに回収するのは至難の業です。SanMoriのスリッカーブラシはそれを見事に解決してくれているので、とっても使いやすいです!
ネコも兼用とは書いてありますが、ネコちゃん用はもう少し目が細かいスリッカーブラシを使用したほうが、毛をしっかり回収することができると思います!
デザインもかわいいので、おすすめです!
TANGLE TEEZER ペットティーザー



こちらはワンちゃん、ネコちゃんにやさしいラバータイプのブラシ!
ブラッシングを嫌がる犬、猫向けに開発されたブラシ!
ペットティーザーはブラシの先が皮膚にあたっても痛くないように設計されているので、ブラッシング心地がとてもやさしいです。
まるまるハウスでペットホテルを利用する子たちは、いつもと違う環境で過ごすことになるので、普段はブラッシングができる子も緊張してしまってできなくなることがあります。
そんな時にこのペットディーザーが活躍してくれて、お散歩後のブラッシングが問題なく行えることが多いです。



Instagram、YouTubeで有名なリーリエちゃんが宣伝しているね!
思わずパケ買いしちゃった!
初心者でも安心!正しいブラッシングのやり方解説


正しい手順で行えば、ブラッシングは愛犬にとって心地よい時間になります。
以下のステップを参考に、優しく丁寧に行いましょう。
1.準備
まずはブラッシングに必要なものをそろえていきましょう!
- 愛犬に合ったブラシ(スリッカー、ピンブラシ、ラバーブラシなど)
- コーム(毛玉チェックや仕上げ用)
- 必要に応じてブラッシングスプレー(静電気防止、毛の絡まりをほぐす)
- ご褒美用のおやつ←重要!
2.声かけ
ブラッシングを始める前に、「ブラッシングしようね」など優しく声をかけ、犬をリラックスさせましょう。落ち着ける場所を選び、飼い主さんもリラックスして臨むことが大切です。
ブラッシング前に飼い主さんが声掛けすることを習慣化し、犬に「なにかいいことがあるかも!」と学習してもらいましょう!
3.ブラッシングのポイント
ブラッシングの基本は、「毛の流れにそって」です。
毛の流れに逆らってブラッシングをすると毛は確かにごっそりと取れるかもしれません。しかし、犬からしたら痛いかもしれないので注意が必要です。
・毛先から根元へ
まずは毛先のもつれを優しくほぐし、徐々に根元に向かってとかしていきます。いきなり根元からとかすと、毛が引っ張られて痛みを感じさせてしまうことがあります。



特に長い毛の犬は古い毛をごっそりとるイメージではなく、少しずつ、少しずつとっていくイメージが大事!
・体の広い部分から
背中など、比較的嫌がりにくい広い部分から始め、徐々に他の部位へ移ります。
落ち着いて、安心している様子が見られるようになってきたら、次の部位に行くようにしましょう。体の広い部分をブラッシングしているときに緊張している姿が見られたら、「今日はここまで」と割り切って終えましょう。



慣れていない子は毎日少しずつがポイント!
・各部位
体の広い部分が終わったら、各部位をブラッシングしていきましょう。お腹(優しく)、足・尻尾(嫌がる子が多いので慎重に)、顔周り(目に注意し、コームなども活用)の順で進めるのが一般的ですが、犬が嫌がらない場所から始めるなど、順番は工夫しましょう。
4.毛玉を見つけた時の対処法
毛玉を見つけたら、無理にブラシで引っ張らないように要注意です。痛みを与えてしまい、ブラッシング嫌いの原因になります。
指で少しずつ分けたり、スリッカーブラシの先端で毛玉の端から少しずつとかしたりします。



ブラッシングに慣れていない犬や、初心者飼い主さんの場合は、迷わず切ってしまうのがおすすめです!
あたふたしてしまい、時間がかかってしまうことがブラッシング嫌いの原因になる可能性があるよ!
5.終わった後のご褒美
ブラッシングが終わったら、「よくできたね!」「気持ちよかったね」とたくさん褒めて、おやつなどのご褒美をあげましょう。ブラッシングが良いことだと関連付けてもらうことが大切です。



関連付けにはやっぱりおやつは最適です!
ブラッシングに慣れてきたり、関連付けがしっかりできてきたら別のご褒美を試してみましょう!
ブラッシングを嫌がる愛犬への対処法・コツ


「ブラシを見ると逃げる」「唸る、噛もうとする」…実は、ブラッシングが苦手な子はとても多いです。でも、諦めないでください!原因を探り、正しいステップで根気強く向き合えば、きっと克服できます。
なぜ嫌がるの?主な原因
原因となりうる事をまとめてみました。愛犬に該当しているかどうか確認してみましょう。
・何をされるかわからない不安: ブラシやこれから起こることが理解できず、怖いと感じている。
・引っ張られて痛い: 過去に毛玉を無理に引っ張られたり、強い力でとかされたりして痛みを感じた経験がある。
・拘束されるのが嫌: その場にじっと留まっていること自体が苦手、自由を奪われる感覚が嫌。
・ブラシが怖い: ブラシの見た目や、体に当たる感覚そのものが怖い、不快。
・体を触られるのが苦手: そもそも体の特定の部分や、全身を触られることに慣れていない、抵抗がある。
・その他: 皮膚に炎症がある、その時の気分が乗らない、場所が落ち着かないなど。



色々な原因があり得るね。



そう!大切なのは愛犬をよーく観察して、原因を正しく知ることが克服への近道だよ!
克服のためのステップ(焦らず、ゆっくり、確実に!):
原因によって細かいアプローチは異なりますが、ここではまるまるハウスが実際に意識して実践していることをご紹介させていただきます!
【ステップ0】体全体を触る練習から
ブラッシング以前に、体のどこを触られても嫌がらないように、日頃から優しく撫でたりマッサージしたりする練習をしましょう。リラックスしている時に、背中、お腹、足先、顔周りなどを優しく触り受け入れてくれたら褒めてあげます。
【ステップ1】ブラシに慣れる練習
まずはブラシを見せて匂いを嗅がせます。犬の近くにブラシを置き、自分から匂いを嗅ぎに来るまで待ちましょう。 無理強いは禁物です。
自分からブラシの匂いを嗅ぎに来たら、すかさず褒めておやつをあげます。「ブラシ=良いことがある」と関連付け、繰り返します。
何度か繰り返して慣れてきたらブラシの背(ピンがない方)や柄の部分で、優しく体を撫でてみます。これも受け入れてくれたら褒めておやつをあげます。
【ステップ2】ブラシを体に当てる練習
いきなりとかさず、「ブラシを当ててもいいかな?」と聞くような気持ちで、ブラシのピンの部分をそっと体に触れさせます。体に触れるだけで十分です。ほんの数秒触れさせて、すぐに離し、できたら褒めておやつをあげます。
背中や腰など、比較的抵抗の少ない部分から始め、徐々に身体側面→首・胸→お腹→頭→足先・耳といった順番で、触れる範囲を広げていきます。
【ステップ3】優しくとかす練習
ブラシを当てることに慣れてきたら、毛の流れに沿って、ほんの少しだけ優しくとかしてみます(一回とかす程度)。
できたらすぐに褒めておやつを与えましょう。
これを繰り返し、少しずつとかす回数や時間を延ばしていきます。
毛玉がある場合は痛みの原因になりやすいので無理にとかさず、手で少しずつほぐします。 難しい場合はカットを検討しましょう。
【成功のための大切な心構え】
・褒めながら笑顔で楽しそうにやるのが一番大切!
飼い主さんが不安そうだったり、イライラしていたりすると、ワンちゃんにも伝わってしまいます。「楽しい時間だよ」という気持ちで、たくさん褒めながら、笑顔で行いましょう。
・1回で全部やろうとしない
ブラッシングに慣れないうちは、完璧を目指さず、短時間(数分でもOK)で切り上げることが大切。その代わり、毎日少しずつ続けることで、習慣化しましょう。
・無理強いは絶対にしない
嫌がる素振りを見せたら、すぐに中断しましょう。「嫌がったらやめてもらえる」と学習することで、逆に安心感に繋がります。
まとめ|ブラッシングを通して素敵なワンワンライフを!


愛犬のブラッシングは、単に毛並みを美しく保つだけでなく、皮膚の健康チェック、病気の早期発見、そして何より愛犬との大切なコミュニケーションの時間です。
ブラッシングが苦手な子も、諦めずに正しいステップで根気強く向き合えば、きっと克服できます。一番大切なのは、飼い主さんが焦らず、笑顔で、楽しむ気持ちで行うこと。
正しい方法と適切な道具選び、そして何より愛情をもって接することで、ブラッシングは愛犬にとっても飼い主さんにとっても、かけがえのない絆を深める習慣になるはずです。
この記事が、あなたと愛犬のより豊かな生活の一助となれば幸いです。

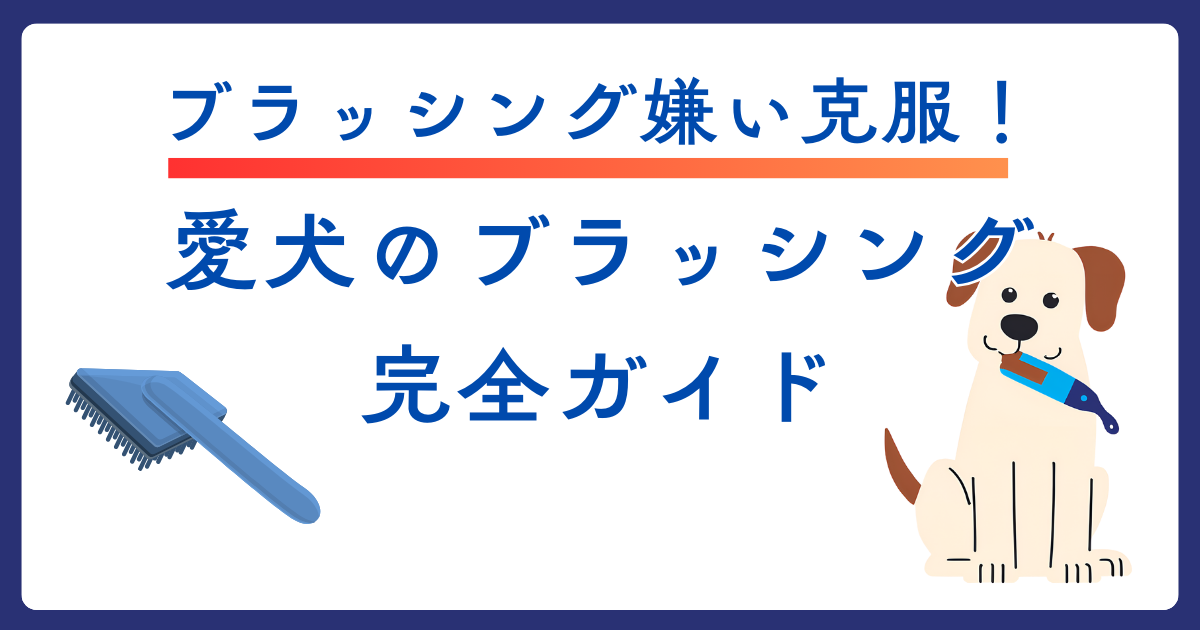


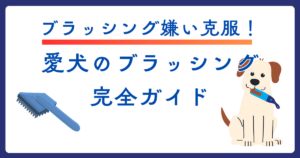
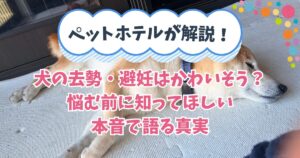
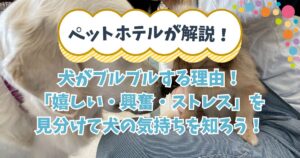


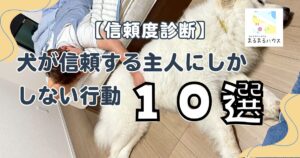

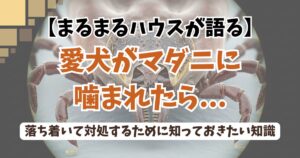
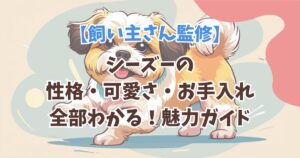
コメント